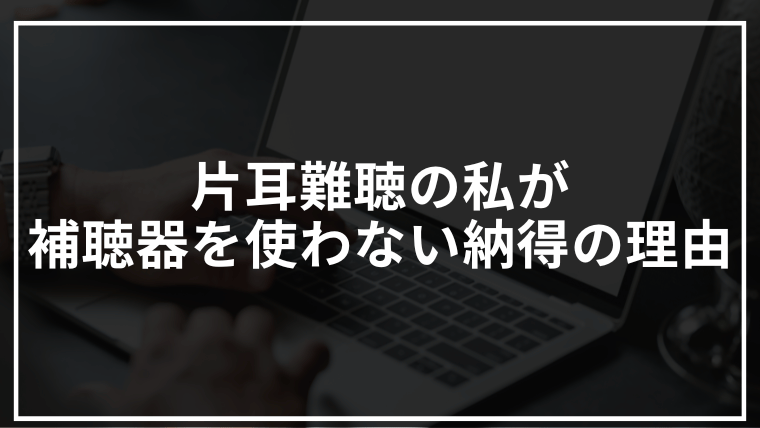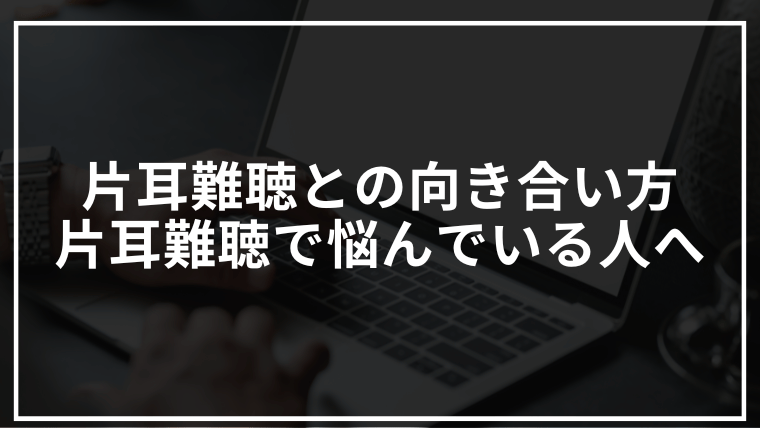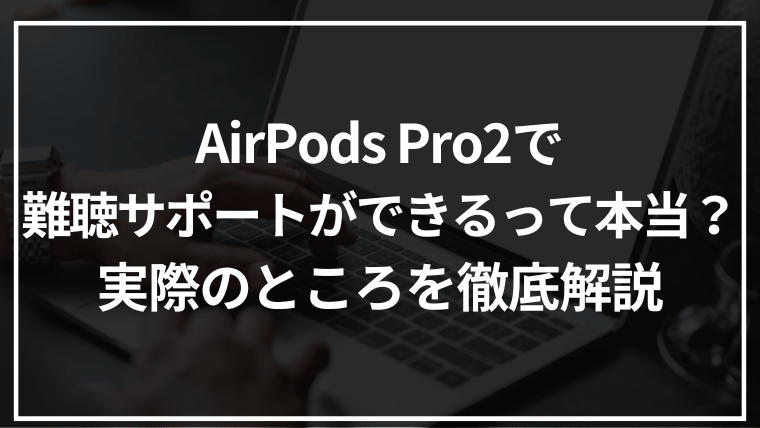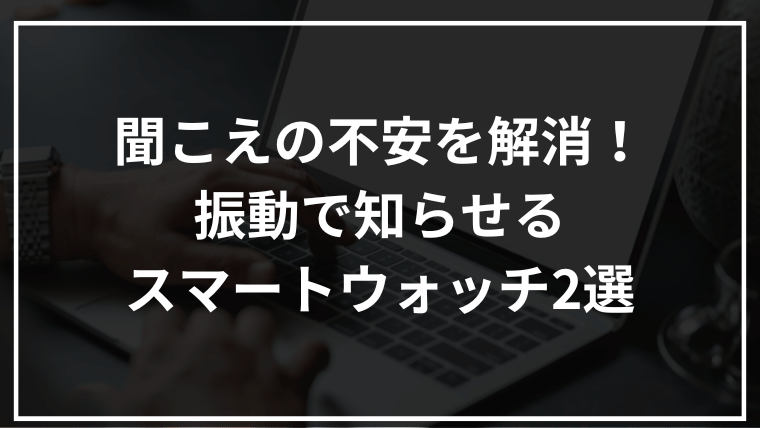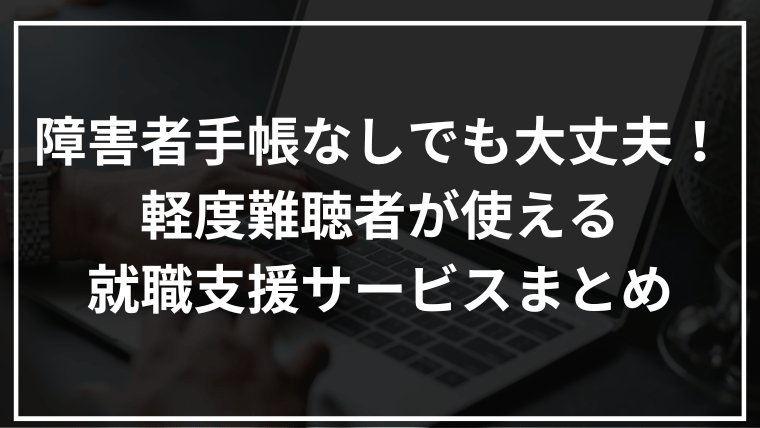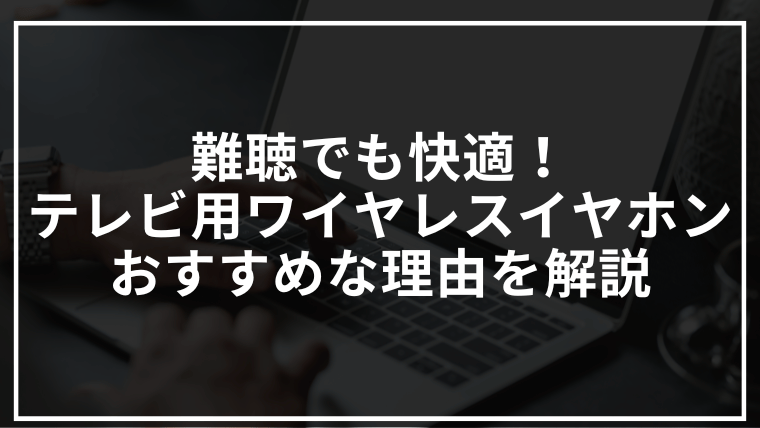難聴だからこそ知っておきたい「就ける仕事」と「就けない仕事」完全ガイド
「難聴があると、就けない仕事ってあるのかな…」
「働きたい気持ちはあるのに、できる仕事がわからない…」

そんな不安や疑問を抱えて、仕事探しに悩んでいませんか?
難聴や聴覚障害があると、
確かに一部の職業には制限があります。
でも、就けない職業がある一方で、
できる仕事・向いている仕事もたくさんあるんです。
この記事では、難聴の方が就きにくい職業7選を法律や制度に基づいて解説しつつ、
逆に難聴でも活躍しやすい仕事や、
働きやすい環境の探し方まで詳しくご紹介します。

難聴でも自分に合った働き方や仕事を見つけたいという悩みを解決します。
難聴だと就けない可能性がある職業7選とその理由
難聴のある方が法的・実務的に就けないことが可能性多い7つの職業について理由とあわせて解説します。
- 自衛官・警察官・消防士など公務系職業
- 航空業界(パイロット・CA)
- 鉄道・運輸系(運転士・整備士)
- 電話対応を主業務とする仕事
- 音声認識が必須な現場作業
- 無線・緊急連絡が必要な職業
- 法律・制度で制限される仕事の一覧
それでは、順番に解説していきます。
① 自衛官・警察官・消防士など公務系職業
自衛官・警察官・消防士といった公務員職は、国家の安全や人命に関わるため、
厳格な身体要件が定められています。
多くの場合、採用試験の応募資格に条件が明記があります。
このような職業では、災害時や犯罪現場などの緊急状況で、
即座に無線や指示に対応できる能力が必須です。
そのため、軽度であっても難聴がある場合は原則として応募ができない可能性があります。
これは決して「差別」という意図ではなく、
任務上の即応性と安全性を守るための必要条件です。
現場では瞬間的な音声のやり取りが命に関わるため、
万が一のトラブルを避けるためでもあります。
なお、こうした職種でも「事務職や総務部門」などの裏方であれば、
聴力条件が緩和されている場合もあります。
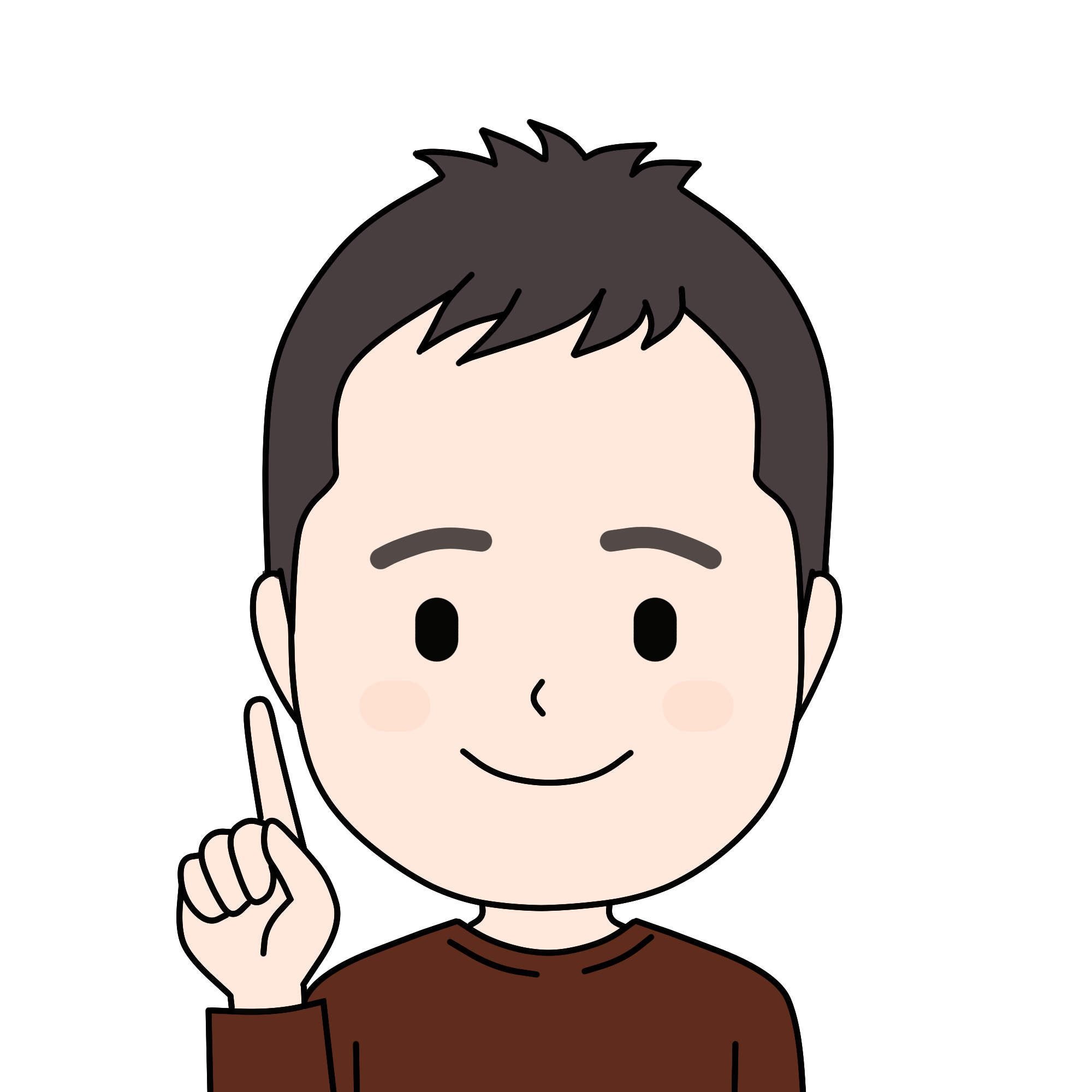
就きたいという気持ちがあっても、
どうしても制度上厳しいことがあるのが現実です。
※就くのが希望であれば、窓口に確認が必須ですね。
② 航空業界(パイロット・CA)
航空機のパイロットやCAも、
聴覚に関する身体条件が厳しく設定されています。
パイロットは航空法に基づく規定により一定の聴力を満たしていなければならず、
難聴の方がこの職業に就くのは非常に難しいです。
パイロットは、飛行中の航空管制との無線交信が命綱になります。
わずかな聞き間違いでも航空事故のリスクを高めるため、
どんなに視力や反射神経が良くても、聴力に問題があると許可が下りません。
| 種別 | 求められる聴力レベル | 対応できる聴力状態 | イメージ |
|---|---|---|---|
| 第1種 (事業用・定期運送用操縦士) | 各耳で ・500Hz1,000Hz、2,000Hz:35dB以下 ・3,000Hz:50dB以下 | 両耳とも高精度な聴力が必要 | 静かな会話やささやき声を 明瞭に聞き取れるレベル |
| 第2種 (自家用操縦士・訓練生) | 両耳で ・500Hz1,000Hz、2,000Hz:45dB以下 ※満たさない場合は、 どちらか一耳が30dB以下で可 または ・後方2mからの会話を両耳で正しく聞き取れること | 片耳が難聴でも もう片耳が良好であればOK | 通常の会話を日常的に 問題なく聞き取れるレベル |

第2種(自家用操縦士・訓練生)であれば、
難聴(軽度難聴)でも免許取得できる可能性があります

キャビンアテンダント(CA)に関しては、お客様との会話や緊急時の避難誘導など、
音声による即時対応が必要となります。
キャビンアテンダントに聴力の数値的な明示基準は示されていませんが、
航空法および運航規程により、「安全な業務遂行に支障がない健康状態」が求められます。
ただし、地上職や空港の事務スタッフなどであれば、
難聴があっても対応可能な職場もあります。

航空業界ってやっぱり憧れの職業の一つですよね。でも、音声でのやり取りが中心なだけに、残念ながらハードルが高め。
夢を支える側で活躍するというルートもありますよ!
③ 鉄道・運輸系(運転士)
鉄道やバス、トラックなどの運輸業界でも
運転士や整備士は国家資格や企業内資格を取得する必要があり、
その条件に「一定の聴力」が含まれています。
就くのが希望であれば、各鉄道会社に確認が必須ですね。
ただし、駅の事務スタッフなどであれば、
難聴があっても対応可能な職場もあります。

鉄道の運転士さん、憧れる人も多い職種です。
機械の異常音を聞くことが仕事の一部になっていたりして、
音が大事な場面が多いです……
④ 電話対応を主業務とする仕事
コールセンター、テレアポ、ヘルプデスクなど、
電話をメインの業務とする職種は、難聴の方にとって非常にハードルが高い仕事です。

理由は単純で、「聞こえること」が業務の前提となっているからです。
また、企業によっては「社内電話の取り次ぎ」を必須にしているケースもあり、
事務職でも電話対応が必要な場面があります。
聴覚にハンディのある人は「電話が取れないこと」が評価に影響する可能性もあります。
最近では、チャット対応やビジュアルサポートに移行している企業も増えてきていますが、
「電話中心の職場」は現時点でも少なくありません。

電話って、難聴の人には天敵みたいな存在ですよね……
ボクの主観だと「電話がメイン業務」でなければ
工夫で何とかなると思います。
⑤ 音声認識が必須な現場作業

工事現場、工場のライン作業、建設現場などの職種では、
現場の「音」で安全確認や指示が行われる場面が非常に多いです。
このような業務においては、音を聞き取ることが「命を守る手段」となるため、
聴覚のハンディがある方にとっては就業が難しいケースがあります。
具体的には、重機の警告音、他作業者からの「ストップ!」といった音声指示、
非常時のサイレンなどを正確に認識できないと、事故につながるリスクが高まります。
特に、騒音が大きく常時インカムで指示を出すような現場では、
補聴器をしていても聞き取ることが困難です。
工場の仕事内容によっては問題ない場合もあるので、
就くのが希望であれば一度、会社に確認が必須ですね。

工場や現場での作業って、「危険を察知する耳」が必要なんですよね。
⑥ 無線・緊急連絡が必要な職業
救急救命士、港湾作業員、警備員の中でも警備指令系、イベント運営スタッフなど、
無線やインカムで指示を受ける職業は難聴の方にはハードルが高めです。
これらの職業では「現場でリアルタイムの音声指示を聞く」ことが求められます。
特に、緊急時に情報が錯綜する場面では、誰がどこにいて、
どんな指示が必要かを瞬時に判断する必要があります。
視覚で代替するのが難しい環境では、
聞き取り能力が直接業務遂行に関わります。
就くのが希望であれば一度、会社に確認が必須ですね。

ボクも一度、イベント運営系のバイトをしようとしたことがあって、
インカム対応が必須って言われて断念しました…。
⑦ 法律・制度で制限される仕事の一覧
就けない理由が「なんとなく」ではなく、法律や制度で明確に定められている職業があります。
| 職業 | 参考の資料 | 内容 |
|---|---|---|
| 自衛官 | 自衛官候補生 身体検査基準(防衛省) | 「正常なもの」と」記載あり |
| 警察官 | 警視庁 採用資格ページ | 「警察官としての職務執行に支障がないこと」と記載あり(警視庁) |
| パイロット | 「一般財団法人 航空医学研究センター」「航空法」 | 第1種(事業用・定期運送用操縦士)または第2種(自家用操縦士・訓練生)によって条件に違いあり。 |
| 鉄道運転士 | 動力車操縦者運転免許に関する省令 | 各耳とも五メートル以上の距離でささやく言葉を明らかに聴取できること。 |
| 消防士 | 名古屋おしえてダイヤル | 名古屋市の消防官採用試験では、「聴力:左右とも正常であること」と明記されています。自治体によって異なり、受験要件か合格基準かも自治体によって異なる。 |
※就職を検討する際は、必ずご自身で最新の情報を確認し、
関係機関へ直接お問い合わせください。
「関係機関に問いあせて合わせてみたけどダメだったから終わり」ではなく、
「別の形で関わる方法はある」と前向きに捉えることが大切です。
これらの職業に就くことが難しい場合でも、
事務職などの間接部門や、関連業界の支援職として関われる可能性は十分にあります。

前向きに捉えることが重要です。
貴方だからこそできる仕事が必ずあります!
難聴の程度によって違う「できる・できない」の境界線

難聴にはさまざまな程度や状態があり、それによって就ける仕事の選択肢が大きく変わります。
- 片耳難聴・軽度のケース
- 中等度・高度難聴の場合
- 補聴器・人工内耳の活用で変わる仕事
- 職場環境次第で対応可能な仕事
それでは、それぞれ詳しく見ていきましょう。
① 片耳難聴・軽度のケース
片耳難聴や軽度の難聴は、健常者と同じように日常生活を送れている方も多く、
「あまり問題がないのでは?」と思われがちです。
たとえば、片耳が難聴だと、
「話しかけられたことに気づかない」「話している相手の方向がわからない」「会議など騒がしい環境での聞き取りが苦手」といった問題が出てきます。
会社によってはその程度の難聴であれば、
一般枠で問題なく採用されるケースが多いかと思います(ボク自身もそうです)
しかし、障害者手帳の取得条件には当てはまらないことが多いため、
「支援を受けづらい」という現実もあります。

ボク自身、片耳難聴者ですが、見た目ではわからないから理解されにくいんですよね…。
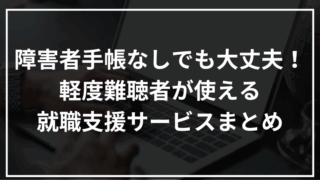
② 中等度・高度難聴の場合
中等度以上の難聴になると、会話の音がほぼ聞き取りづらくなり、
日常会話や職場でのやり取りが難しくなります。
この段階では、補聴器や筆談、チャットツールなど、
明確なサポートが必要になります。
たとえば、一般的なオフィス勤務でも「朝礼が聞き取れない」「電話ができない」「隣席との会話が困難」といった問題が頻出します。
これにより、適応できる職業はかなり限定されてきます。
就ける職業としては、データ入力、経理、ライター、翻訳、IT系開発職など、
「音声でのやりとりが少ない職種」がメインになります。

中等度以上になると、正直つらい場面は増えます。
ただ、支援制度が使えるようになる分、ちゃんとした企業ならサポート体制も整ってるので、逆に働きやすくなったと感じる人も多いんですよ!
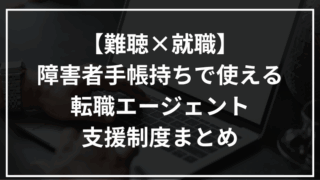
③ 補聴器・人工内耳の活用で変わる仕事
補聴器や人工内耳は、
聞こえに課題のある方にとって非常に心強いアイテムです。
これらのデバイスによって「対応可能な職種」が大きく広がる可能性があります。
たとえば、補聴器を使用して通常会話がある程度こなせるようになれば、
事務職、接客、営業など、対人コミュニケーションが含まれる職種にもチャレンジできる可能性があります。
ただし、補聴器にも限界があります。
雑音の多い場所や会話が複数交錯する場面、スピーカー越しの声などには弱く、
環境次第ではストレスの原因になることもあります。
また、人工内耳は手術を伴うため、導入までに時間がかかりますが、
重度難聴でも音声の一部が認識できるようになるため、再就職のチャンスが広がったという声もあります。

ボクは片耳難聴ですが、
補聴器を入手して仕事に対する不安感が減少しました!
でも過信は禁物。
自分の聞きやすい環境を作る工夫は続けていくことが大切にいています。
④ 職場環境次第で対応可能な仕事

難聴の方にとって「向いている/向いていない」は、単に職種だけではなく、
その職場の配慮・環境整備レベルによっても大きく変わります。
たとえば、同じ「事務職」でも、電話応対が必須かどうか、
情報共有がチャット中心か、会議に字幕ツールがあるかなどで、働きやすさはまったく違ってきます。
具体的には以下のような取り組みがあります:
- 会議のリアルタイム文字起こし(UDトークなど)
- チャットやメールでの指示伝達の徹底
- 電話応対業務の分担調整
- ピクトグラムやLED表示によるアナウンス
このような環境が整っている職場であれば、軽度〜重度の難聴であっても、
自分らしく働くことが可能になります。

環境ってほんと大事。やる仕事は同じでも、コミュニケーションがスムーズにできるだけでストレスが全然違うんです。
入社前に「配慮してもらえるかどうか」は確認しておくのがオススメです!
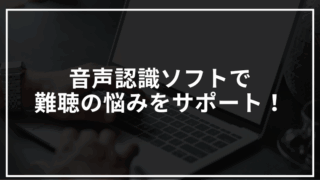
難聴でも就ける!働きやすい仕事10選
難聴があっても働きやすく、活躍している人が多い仕事を10個ご紹介します。
- 在宅ライター
- プログラマー・エンジニア
- データ入力・経理・事務
- デザイナー・クリエイター職
- 検査技師・技術系医療職
- 翻訳・字幕制作
- 福祉・支援員など当事者支援職
- カスタマーサポート(チャット対応)
- マッサージ・リラクゼーション職
- 公的機関の事務補助職など
それぞれの仕事について、特徴や向いている理由を解説します。
① 在宅ライター
文章を書くことが好きな方には、
ライターや校正者の仕事が非常におすすめです。
基本的にパソコンでの作業が中心で、音声のやり取りはほぼ発生しません。
クライアントとのやりとりもメールやチャットが中心です。
在宅で働くことも可能なので、
周囲の音環境に左右されず、自分のペースで仕事ができるのもメリットです。
記事執筆、コピーライティング、セールスページ作成など、得意な分野を選べば専門性も高まります。

ボクは片耳難聴です。
文章を書く(構成する)のが好きでブログを始めました。
② プログラマー・エンジニア

IT分野は難聴の方にとってチャンスの宝庫です。
プログラマーやエンジニアは、パソコンでのコーディングやシステム構築が主な業務で、コミュニケーションもテキストベースで進むことが多いです。
Slackやチャットツール、タスク管理ツール(Trello、Backlogなど)を使えば、口頭でのやりとりが不要で業務を完遂できます。
さらに、在宅勤務やフルリモートも広がっており、環境を自分で整えられるのも魅力です。
未経験からでもスクールや支援制度を利用すれば学びながら就職可能で、
将来性も高い分野です。

音じゃなくて“コード”でやり取りする仕事。
これはほんとに最強です。IT系にちょっとでも興味があるなら、全力でおすすめしたい!
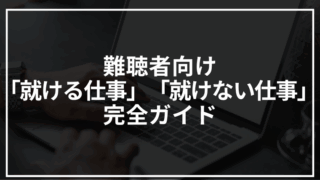
③ データ入力・経理・事務
データ入力や事務職は、集中力と正確さがあれば、聴覚に関係なく活躍しやすい職種です。
特に最近は電話対応を分担制にしている職場も増えており、「電話なしの事務職」を選べば、非常に働きやすい環境になります。
経理も同様で、エクセルや会計ソフトなどを使って黙々と数字と向き合う作業が中心。
社内のやり取りもチャットで済むケースが多く、聴覚に頼らず業務が進められます。
簿記やMOSなど、就職に有利な資格を取得することで、
正社員登用や年収アップも目指せます。

経理職は属人化しやすい業務が多いので、
会社にとって替えが効きにくい(=代わりを見つけにくい)貴重な人材になることができます。
④ デザイナー・クリエイター職

グラフィックデザイナー、Webデザイナー、イラストレーターなどのクリエイティブ職も、難聴の方に人気の職種です。
視覚的な作業が中心で、静かな環境で作業がしやすいため、
聴覚の影響を受けにくいのが特徴です。
クライアントやチームとのやり取りも、指示書やチャットが主流で、文章での意思疎通ができれば問題ありません。
納期と成果物で評価される職種なので、自分のペースで働きやすいです。
最近はオンライン講座や独学ツールも豊富なので、
スキル習得にも取り組みやすく、副業としても人気です。

静かにコツコツ作業したい人にはピッタリ!ボクはデザインソフトが苦手で断念したけど、
センスがある人はチャレンジする価値大アリです!
⑤ 検査技師・技術系医療職
医療現場でも、音声によるやりとりが少ない「検査技師」などの職種は、
難聴の方でも活躍できるフィールドです。
具体的には、臨床検査技師、放射線技師、視能訓練士などが挙げられます。
これらの仕事では、患者さんと接する場面もありますが、口頭指示が少なく、作業内容がルーチン化されているため、
コミュニケーションの負担が比較的少ない傾向があります。
もちろん国家資格が必要になりますが、専門学校や養成校で学ぶことでキャリアチェンジも可能です。
医療分野での安定感や社会的意義もあり、やりがいを感じられる仕事です。

困っているの人の気持ちを理解できる難聴者だからこそ、
向いてる人多いと思います!
⑥ 翻訳・字幕制作
翻訳や字幕制作の仕事は、音ではなく「言葉そのもの」と向き合う職種です。
特に文書翻訳やローカライズ、映画やアニメの字幕制作などは、視覚的な作業が中心で、聴覚の影響を受けにくいのが特徴です。
業務は主にパソコンで完結し、指示や納品もチャットやメールで行われるため、音声によるやり取りがなくてもまったく問題ありません。
外国語が得意な方や、コツコツした作業が好きな方にとっては天職になる可能性もあります。
最近では、YouTubeや企業PR動画の字幕作成など、副業的な需要も急増しています。
語学力を活かしつつ、自宅でできる自由度の高さも魅力です。

クリエイト系(デザインなど)に加えて、このスキルをかけ合わせることができれば
まさに、「鬼に金棒」です!
⑦ 福祉・支援員など当事者支援職
聴覚障害を持つ当事者だからこそ、その経験を活かして働けるのが「支援職」です。
福祉施設、医療機関、教育現場、相談支援事業所などでは、難聴の当事者が、同じ境遇の人たちをサポートする「ピアサポート」の役割を担うケースもあります。
仕事内容は多岐に渡りますが、主に手話での対応、福祉制度の案内、学校・職場での支援活動、就労移行支援などが挙げられます。
「伝える力」よりも「寄り添う力」が求められる仕事で、
聴覚障害への理解が深いほど適任となります。
福祉系の資格(社会福祉士、精神保健福祉士、サービス管理責任者など)があれば、
活躍の場はさらに広がります。

当事者だからこそできる仕事って、ありますよね。
自分の経験が誰かの役に立つって、めちゃくちゃやりがいになりますよ…!
⑧ カスタマーサポート(チャット対応)

カスタマーサポートというと電話対応のイメージが強いかもしれませんが、
最近では「チャット専用オペレーター」という職種が注目されています。
ユーザーからの質問に、LINEやWebチャットで答える業務で、音声対応は一切不要な環境も増えています。
特にECサイトやデジタル系サービスでは、カスタマーサクセスをチャットで対応する企業も増加中。
タイピング速度や正しい日本語のスキルがあれば、未経験でも採用されやすい業種です。
もちろん、対応マニュアルがあったり、テンプレートが整っている職場を選ぶことで、
よりストレスなく働けるでしょう。

「電話じゃなくてチャット」が当たり前になってきてる今、これは本当にありがたい流れです!
人と関わるのは好きだけど、電話が苦手な人にはぴったり!
⑨ マッサージ・リラクゼーション職
国家資格である「あん摩マッサージ指圧師」や、
リラクゼーション業界で活躍するセラピストも、難聴の方に向いている職種です。
施術中の会話は少なく、身体感覚や観察力が求められるため、視覚や触覚が優れている方が重宝されます。
また、聴覚障害者向けの医療マッサージや福祉施設での施術など、障害者コミュニティの中で活躍している方も増えています。
国家資格を取得すれば、独立開業も視野に入れられ、手に職をつけて働けるのも大きな魅力です。
リラクゼーション施設や温浴施設などでは、コミュニケーションが最小限で済む現場もあるため、職場選びさえ間違えなければ非常に働きやすい環境です。

耳よりも“手”が大事な仕事。集中力と丁寧さが活かせるので、
黙々と何かに打ち込みたい人にもオススメですよ!
⑩ 公的機関の事務補助職など
役所や官公庁、学校などの「事務補助職」も、難聴の方が安心して働きやすい職場の一つです。
書類整理、資料作成、データ入力などの仕事が中心で、ルーチンワークが多く、
静かな環境であることが多いです。
また、障害者雇用を積極的に進めている自治体も多く、面接の段階から「配慮事項」を共有して採用されるケースもあります。
公的機関なので、安定性や福利厚生の面でも安心できるのがポイントです。
パートや嘱託職員としてのスタートでも、経験を積めばステップアップも可能。
地域で長く働きたい人に向いています。

「静かに落ち着いて働きたい」って人には、公的機関は本当におすすめです!
ボクの友人も区役所で働いてて、めちゃくちゃ快適って言ってました!
就けない仕事から脱出するための5つの戦略

「できない仕事」にとらわれず、自分に合った働き方へシフトしていくための5つの具体的な戦略を紹介します。
- 資格取得で選択肢を広げる
- 転職エージェント・支援サービスを活用
- 合理的配慮がある職場を探す
- 働き方を変える(在宅・時短など)
- 体験談をもとに自分に合う仕事を見つける
それでは順番に解説していきます。
① 資格取得で選択肢を広げる
難聴があると「仕事の幅が限られる」と思われがちですが、資格を取得することで「自分に合った仕事に就ける可能性」は大きく広がります。
たとえば、以下のような資格は難聴の方に向いていて、企業からのニーズも高いです:
| 資格名 | 活かせる職種 | 特徴 |
|---|---|---|
| 日商簿記 | 経理・会計事務 | 数字に強くなれば安定職に就きやすい |
| MOS(Office資格) | 事務・データ入力 | ExcelやWordのスキル証明ができる |
| Webクリエイター能力認定試験 | Web制作・デザイン | HTML/CSSのスキルを証明できる |
| 登録販売者 | ドラッグストア勤務 | 座学中心で取得しやすく、国家資格 |
| あん摩マッサージ指圧師 | リラクゼーション職 | 身体感覚重視、音声に頼らない |
こうした資格を取ることで、「障害を理由に断られた職種」でも再チャレンジできる可能性があります。
通信講座や支援制度も充実しているので、無理なく学べる環境も整っています。

私も日商簿記を取りましたが、それだけで面接の通りが全然違いました!
「できること」を増やすって、やっぱり強いんですよね。
② 転職エージェント・支援サービスを活用

「一人で仕事を探すのは不安…」「自分に合う職場がわからない…」という方には、
障害者向けの転職支援サービスや就労移行支援の利用がとてもおすすめです。
たとえば障害者手帳を所持している方には、以下のような転職支援サービスがあります:
- atGP(アットジーピー):障害者専門の転職エージェント。大手企業の求人多数。
- dodaチャレンジ:キャリアカウンセリングあり。非公開求人も豊富。
- LITALICOワークス:支援員と一緒に職場体験や実習も可能。
- ハローワークの障害者窓口:公共の支援機関。求人紹介や模擬面接サポートも。
これらのサービスを使えば、「自分の聴力に合った業務」「配慮のある職場」を紹介してもらえるので、安心して就職活動が進められます。
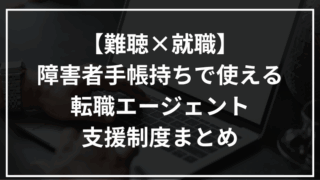
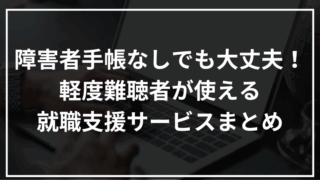

ボクも転職エージェントを使って面談したことがありますが、
丁寧に話を聞いてくれて安心できました。
自分だけで頑張らないこと、めっちゃ大事です!
③ 合理的配慮がある職場を探す
就職活動の際に重要なのが、「その会社がどれだけ障害に配慮してくれるか」です。
最近では「合理的配慮を提供すること」が企業の義務となっており、
対応力のある企業は増えています。
合理的配慮の例
- 電話応対業務を別の社員に振る
- 会議内容をチャットや文書で共有
- リアルタイムの文字起こしツール(UDトーク)を使用
- 作業環境の静音化・照明調整
求人票や会社説明会で「ダイバーシティ&インクルージョン」「障害者雇用の実績」を確認することで、
配慮ある職場を見つけやすくなります。

採用前に「どんな配慮が可能ですか?」ってちゃんと聞いてOKです!
逆にそれに答えてくれない会社は、入社後に苦労する可能性高いので注意です!
④ 働き方を変える(在宅・時短など)
「今までの働き方」では難しかったことも、働き方そのものを変えることで、グッとハードルが下がることもあります。
特におすすめなのが、以下のような働き方
- 在宅勤務(リモートワーク)
- 週3〜4日のパート勤務
- フレックスタイム制度の活用
- クラウドソーシングを使った業務委託
音環境をコントロールできる在宅勤務なら、会話に気を使うことも少なく、集中して作業ができます。
クラウドワークスやランサーズなどのサイトで仕事を受注すれば、自分の得意を活かして収入を得ることも可能です。

自分にとって無理せず働ける形があると、ほんとに心が楽になりますよ。
⑤ 体験談をもとに自分に合う仕事を見つける
一番のヒントになるのが、「同じ難聴の人がどんな仕事をしているのか」を知ることです。
ネット上にはたくさんの体験談があり、自分に近い境遇の人のリアルな働き方から大きな学びが得られます。
たとえば、Twitterやnote、YouTubeなどでは、難聴当事者が
- なぜこの仕事を選んだか
- 入社後にどんな工夫をしているか
- 職場でのストレスとの向き合い方
といった情報を発信しています。
こうした声を知ることで、
「この仕事なら自分にもできそう!」という気づきが得られますし、勇気にもつながります。

ボクも最初は他の人のブログを読んで「おぉ、めちゃくちゃ参考になる!」って思ったのがこのブログの始まりでした。
情報を取りに行くことって、本当に大事です!
難聴の就職・転職でよくある質問とアドバイス

ここでは、難聴の方が就職活動や転職の際によく抱える疑問に、わかりやすく答えていきます。
- 障害者手帳は必要?
- 面接でどう伝えればいい?
- 片耳難聴でも障害者雇用に入れる?
- 企業の選び方は?
- 職場でのコミュニケーション対策は?
では、ひとつずつ見ていきましょう。
① 障害者手帳は必要?
結論から言うと、
「障害者手帳があれば得られるサポートは確実に広がります」。
障害者手帳を持っていれば、「障害者雇用枠」での就職が可能になり、以下のようなメリットがあります
- 配慮ある職場で働ける
- 税金や交通機関の割引が受けられる
- 障害年金の対象となる場合もある(働いている=障害年金がもらえない、というわけではありません。)
「手帳を持ってると働ける仕事が限定されるのでは?」と心配する声もありますが、
逆に“自分を理解してくれる会社と出会える”チャンスが増えると考えて大丈夫です。

障害者手帳を取得することで、「配慮のある職場」に出会えるようになるチャンスの幅が広がるということですね!
② 面接でどう伝えればいい?
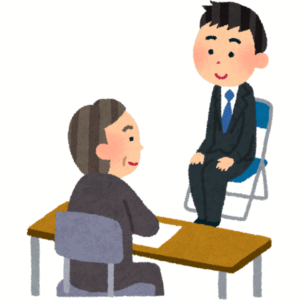
面接では、「自分の聞こえの状態を正直に、かつ前向きに」伝えることが大切です。
伝えるポイントは以下の3点
- 聞こえの程度(片耳だけ/会話はできるが騒音に弱いなど)
- 配慮してもらいたいこと(席の位置、資料の共有など)
- それによって業務がどう影響するか(問題ない、工夫で対応しているなど)
たとえば、「私は左耳が聞こえづらいですが、右耳では問題なく会話ができます。
会議や打ち合わせでは資料を見ながら進めてもらえると安心です」というように、「困りごと+対応方法」をセットで伝えると好印象です。
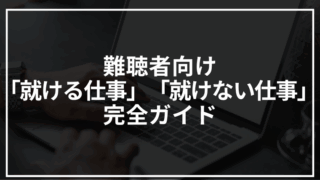

「申し訳なさそうに話す」のではなく、「こうしてもらえたらありがたいです」と笑顔で言うのがコツ!
実際、採用側もちゃんと聞いてくれますよ。
③ 片耳難聴でも障害者雇用に入れる?
結論から言うと、片耳難聴だけでは障害者手帳の対象外になることがほとんどです。
手帳の取得条件は両耳での聞こえの平均が60dB以上(高度難聴)など、ある程度の基準があるためです。
しかし、手帳がなくても「合理的配慮」を求めることは可能です。
企業によっては、「片耳難聴で聞き取りにくい」と伝えることで、面接や職場での対応を柔軟にしてくれるケースもあるので、まずは相談してみましょう。
④ 企業の選び方は?
難聴の方が企業を選ぶときは、以下のようなポイントをチェックしましょう
- 障害者雇用の実績があるか
- ダイバーシティ&インクルージョンを掲げているか
- メイン業務で支障がないか確認
- 職場見学や面談で配慮を確認できるか
転職サイトで「障害者雇用」で検索すると、こうした情報が事前に確認できることが多いです。
また、口コミサイトやSNSで「その会社で働いている難聴の人の声」を探すのもおすすめです。

企業のHPだけじゃ見えないことも多いので、
「実際に働いてる人の体験談」はめっちゃ参考になりますよ!
⑤ 職場でのコミュニケーション対策は?
難聴があると、「ちゃんと伝わっているかな?」「聞き返すのが申し訳ない…」と悩むことが多いですよね。
でも、ちょっとした工夫でストレスはぐっと減らせます👇
- 可能であれば口の動きが見える位置に座る
- 大事なやり取りはチャット・メールに残す
- 会議には文字起こしツール(UDトーク)を活用
- 「すみません、もう一度お願いします」と言える関係性を作る
また、職場の人に「聞こえにくいことがあるので、ゆっくり話してもらえると助かります」と伝えるだけで、空気がぐっと変わります。
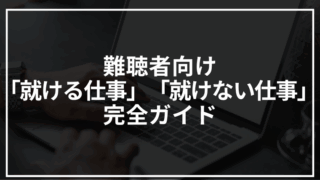

“何度も聞き返していい空気”を作れると、本当に働きやすくなります。
最初のひと言、勇気いりますけど、
言ってみると案外あっさり受け入れてくれますよ!
まとめ:難聴でも「働ける場所」は必ずある
この記事で紹介したように、難聴があると確かに一部の職業に制限はあります。
でも、だからといって人生の選択肢がなくなるわけではありません。
あなたが今どんな聞こえの状態でも、
- 自分の得意なことを活かす
- 支援を上手に利用する
- 「できる環境」で働く
という考え方さえ持てれば、仕事の幅はどんどん広がっていきます。
世の中には「健聴者が当たり前」とされる職場もまだ多いですが、
それ以上に、あなたのことを理解して、必要な配慮をしながら「一緒に働きたい」と思ってくれる会社も必ずあります。
もし今、「どんな仕事ができるかわからない」「ひとりで探すのが不安」という気持ちがあるなら、
就労支援サービスや障害者専門の転職エージェントに頼るのも大きな一歩です。
あなたの「働きたい」という気持ちは、きっとどこかで届きます。
どうか、自分の可能性を閉じないで。
ゆっくりでいいので、一歩ずつ「自分らしい働き方」を見つけていきましょう。

この記事が、あなたの未来をほんの少しでも明るくするきっかけになれば、嬉しいです。