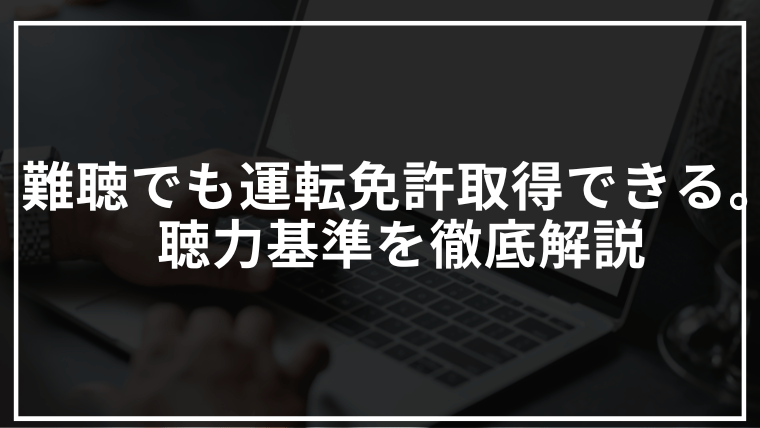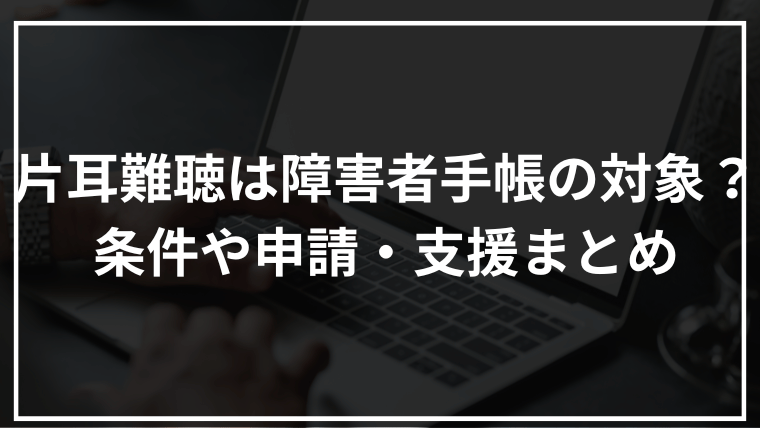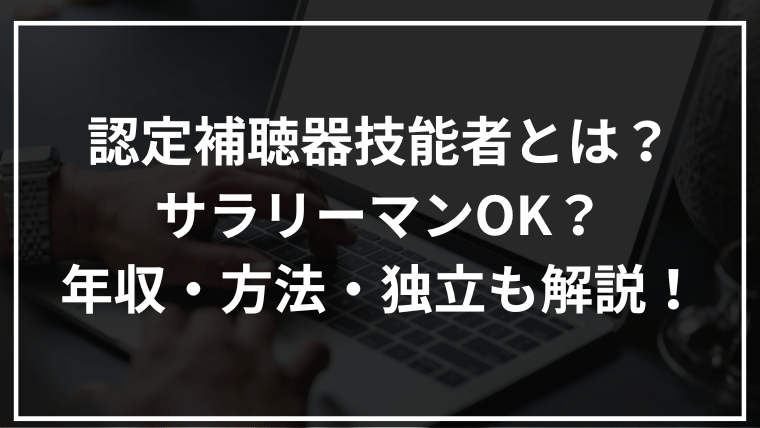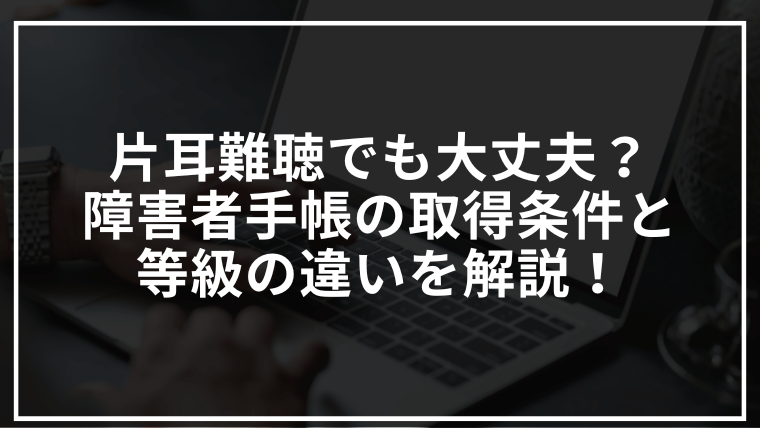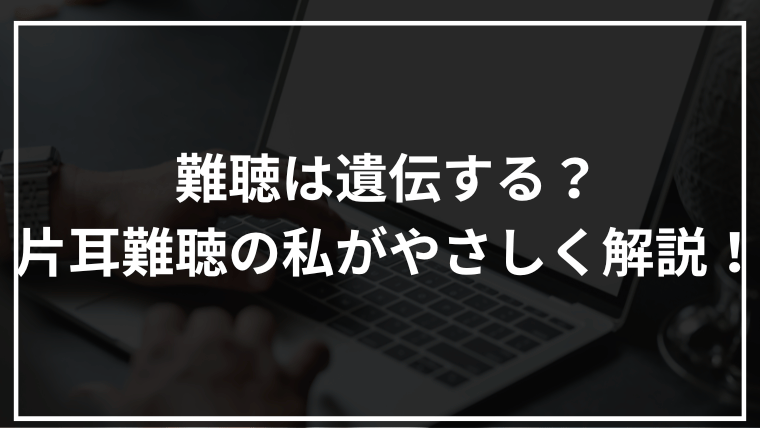自分も対象?補聴器購入で使える医療費控除と補助金を解説
補聴器は高価で、購入をためらう方も多いかもしれません。
しかし実は、医療費控除や補助金制度を活用することで、
費用を大きく抑えることができます。
この記事では、2025年時点の最新情報をもとに、
補聴器の購入時に使える制度を初心者にもわかりやすく解説していきます。
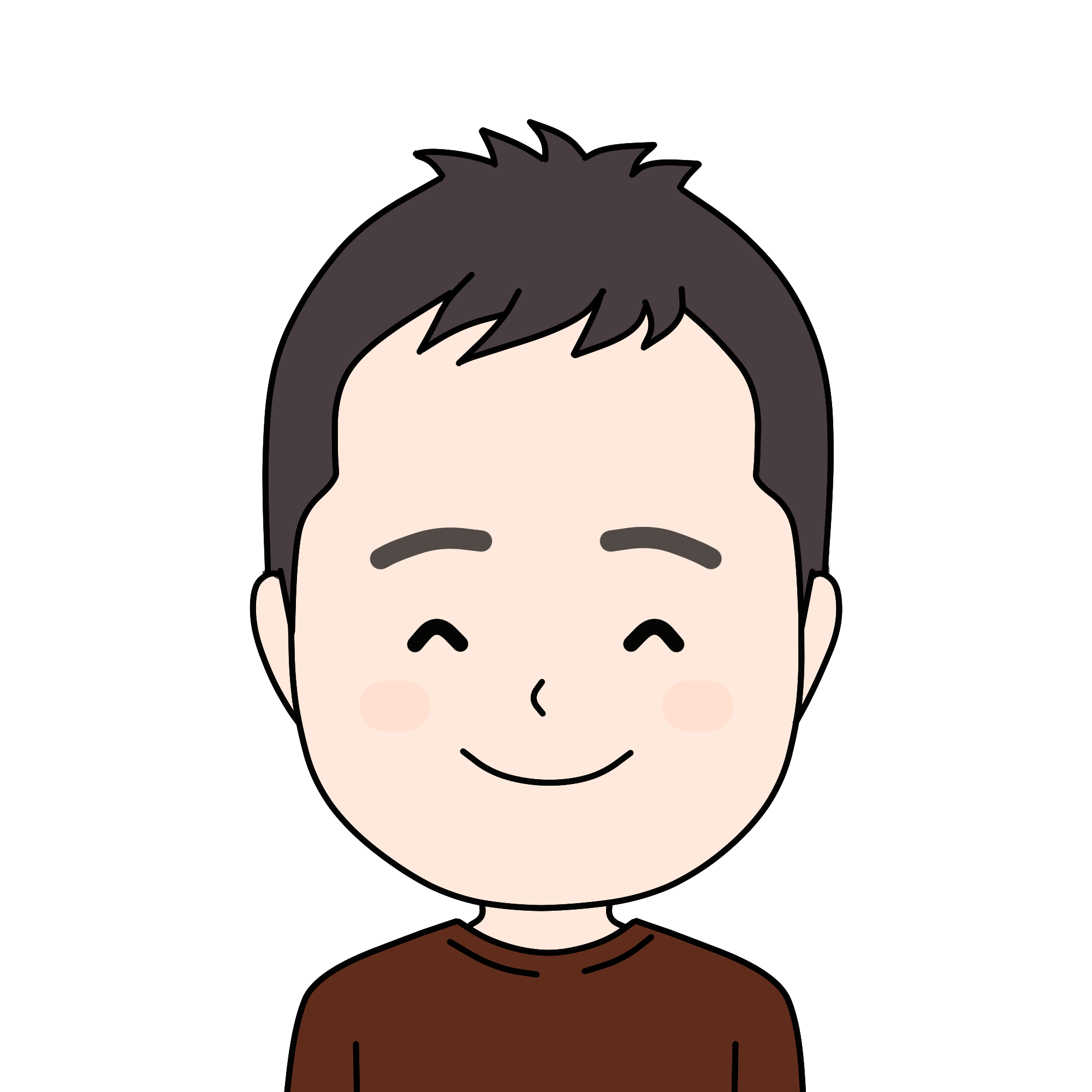
対象条件・手続きの流れ・申請時の注意点まで、
くわしく紹介しますので、ぜひ最後までご覧ください。

医療費控除の対象になる補聴器とは?医療費控除の対象者は?
医療費控除の対象となる補聴器は、
「医師の診断に基づいて、治療に必要と認められた補聴器」に限られます。

すべての補聴器が、
医療費控除の対象になるというわけではないのですね。
医療費控除の対象者は?
病院で補聴器の必要性が確認された場合、
耳鼻科の専門医が「補聴器適合に関する診療情報提供書」という書類を作成します。
この書類は、日本耳鼻咽喉科学会が定めたフォーマットに準じており、
正式な医療書類として扱われます。
ただし、「聞こえにくいから買った」だけでは控除の対象にはなりません。
治療の一環として、医師が適合確認を行い、
証明書を発行していることが前提です。
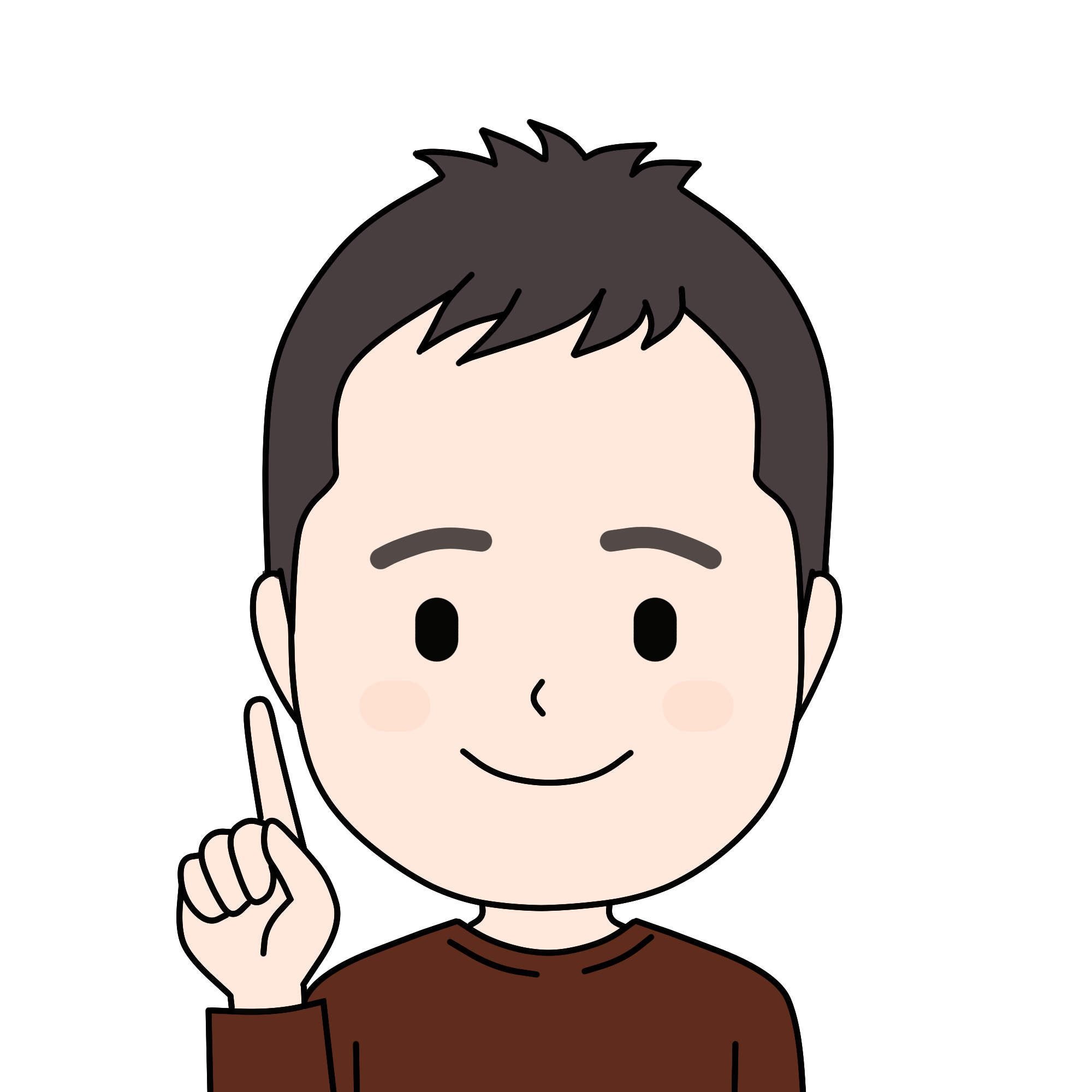
家電量販店やインターネット通販で購入した場合は、
必要書類の発行ができない可能性があるため注意しましょう。
医療費控除の条件と必要書類をわかりやすく解説
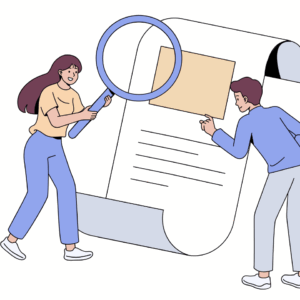
医療費控除を受けるには、次の3つの条件をすべて満たす必要があります。
- 医師の診断と「補聴器適合に関する診療情報提供書」の発行
- 認定補聴器専門店など、医療目的の店舗での購入
- 補聴器の購入費が記載された領収書の保管
これらが揃っていなければ、たとえ高額な補聴器でも控除は認められません。

なかでも診療情報提供書は事前に発行してもらう必要があるため、
購入前に耳鼻科の補聴器相談医に相談し、
診断と書類作成を依頼しておきましょう。
医療費控除の申請手順とスケジュール
医療費控除の申請は、
確定申告の時期(通常2月中旬〜3月中旬)に行います。
手続きの流れは以下のとおりです。
- 補聴器相談医に診察を受け、「補聴器適合に関する診療情報提供書」を取得
- 認定補聴器専門店で購入し、領収書や明細書を保管
- 確定申告時に、必要書類一式を税務署へ提出
申告は、e-Tax(電子申告)・郵送・窓口持参のいずれかで行えます。
在宅で済ませたい方は、マイナンバーカードの準備を忘れずに。
補聴器購入でいくら戻る?還付金の計算例
具体的にどのくらいの金額が還付されるのかは気になるところです。
以下のケース例をご覧ください。
- 年収:400万円
- 補聴器代:25万円
- 控除対象額:25万円 − 10万円(基準額)= 15万円
- 還付金:15万円 × 所得税率10% = 約15,000円
控除対象は「自己負担した医療費 − 10万円 or 所得の5%」のいずれか低い方が基準です。
人によって差はありますが、
数千円〜数万円の還付が期待できます。
補助金は国と自治体の2つの制度がある
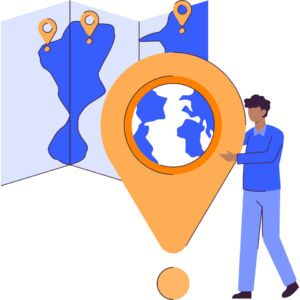
補聴器の補助金には、国の制度(障害者総合支援法)と、
自治体独自の制度の2種類があります。
国の制度である「補装具費支給制度」は、身体障害者手帳を持っている人が対象です。
これは原則として、中等度〜重度の難聴と認定された方に限られます。

国の制度では、
世帯収入によって自己負担額が変わる点にも注意しましょう。
一方、自治体によっては、
手帳がなくても軽度〜中度の難聴に補助金を出している場合があります。

対象者や条件は自治体が自由に設定しています。
金額や条件は地域ごとに大きく異なるため、
購入前に自治体の福祉課へ確認することが大切です。
医療費控除と補助金は併用できる?
医療費控除と補助金の併用は可能です。
ただし、注意点として、補助金で支給された金額は控除の対象になりません。
つまり、実際に自己負担した金額だけが控除対象になります。
たとえば、補聴器が20万円で補助金が10万円支給された場合、
医療費控除の対象は残りの10万円分になります。

申請の順番は「補助金 → 医療費控除」と覚えておきましょう。
補助金申請でよくあるミスと注意点
補助金は購入前に申請することが原則です。
「あとから申請すればいい」と思って先に購入してしまうと、
支給対象外になる可能性があります。
以下の書類を事前に準備しておくことが大切です。
- 補聴器相談医による診療情報提供書
- 補装具交付意見書(障害者手帳関連)
- 見積書・領収書(補聴器の記載があるもの)

また、自治体ごとに制度内容が異なるため、
必ず窓口や公式サイトで確認してください。
よくある質問Q&A|制度の疑問をまとめて解決!
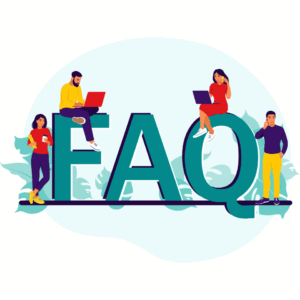
- Q. 電池代や修理費も控除の対象になりますか?
-
原則対象外ですが、補聴器と同時購入し、領収書に明記されていれば認められる可能性があります。
- Q. 補聴器を返品した場合はどうなりますか?
-
返品した金額は控除対象から外れます。すでに申告済みの場合は、修正申告が必要です。
- Q. 家族の分をまとめて申告できますか?
-
同一生計であればまとめて申告可能です。支払者と申告者が異なる場合は、証明書類の提出が求められることがあります。
まとめ|制度を知って賢く補聴器を選ぼう
補聴器は高価な医療機器ですが、
制度を活用すれば費用を大きく抑えることができます。
ただし、「誰が対象になるのか」「どの順序で申請すべきか」といった情報を知らずに購入してしまうと、
損をしてしまう可能性もあるため注意が必要です。
購入前に、医師や自治体へ相談し、必要書類や条件を確認することで、
制度を最大限に活かすことができます。

この記事を参考に、ぜひ賢く補聴器を選び、
安心して聞こえのサポートを受けてください。
参考文献
- 厚生労働省「医療費控除のあらまし」
医療費控除の仕組みや対象条件、申告方法についての公式解説。 - 厚生労働省「障害者総合支援法に基づく補装具費支給制度」
補聴器など補装具の支給対象、手続き、障害等級の基準に関する制度資料。 - 日本耳鼻咽喉科学会「補聴器適合に関する診療情報提供書の運用」
補聴器相談医が発行する書類のガイドラインと目的を記載した文献。 - 国税庁「確定申告等作成コーナーの利用案内」
医療費控除のオンライン申告に関する操作マニュアルや注意点の情報源。 - 各地方自治体(例:東京都福祉保健局、札幌市障がい福祉課など)
地域ごとの補助金制度・支給条件・所得制限などを掲載した公式資料。