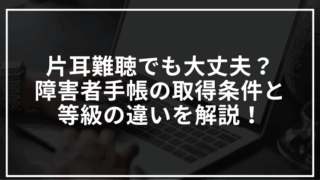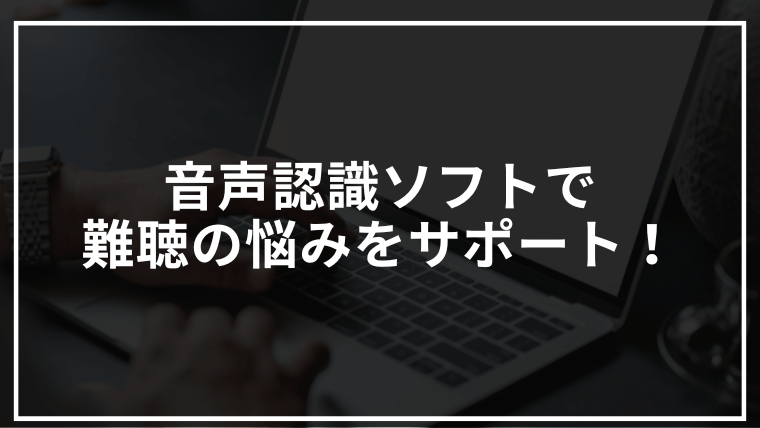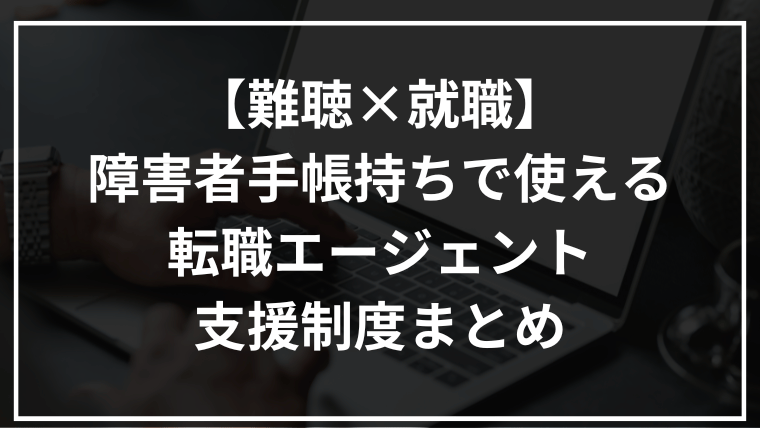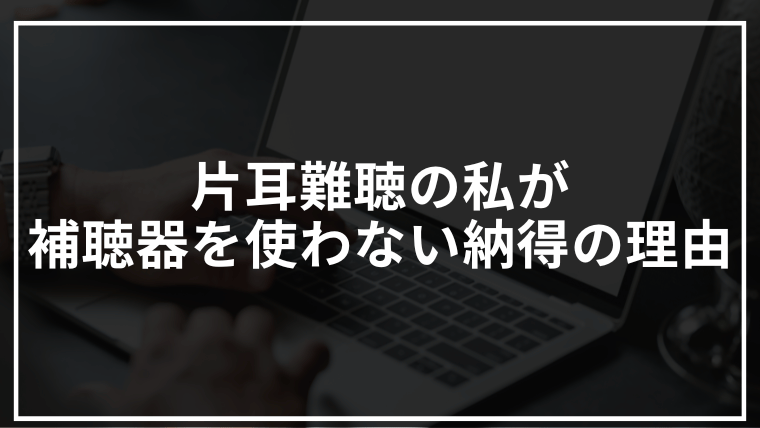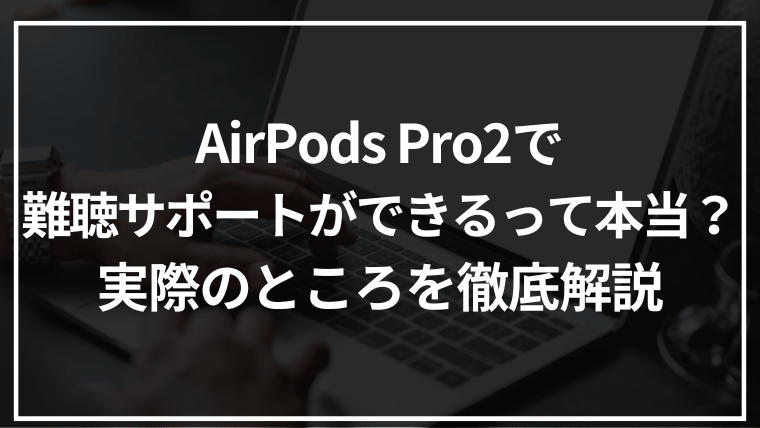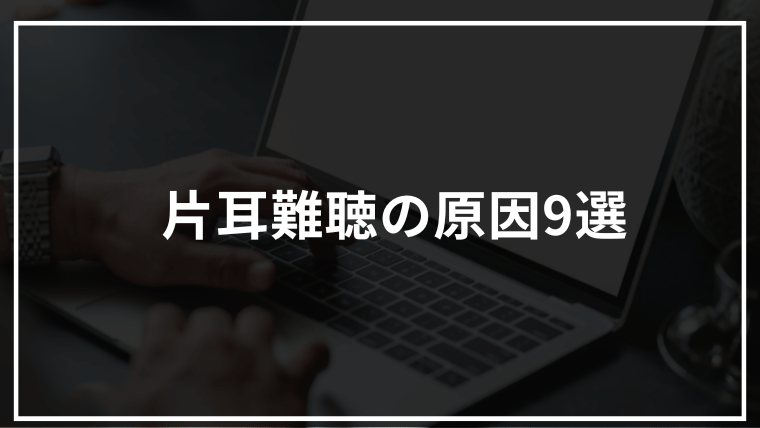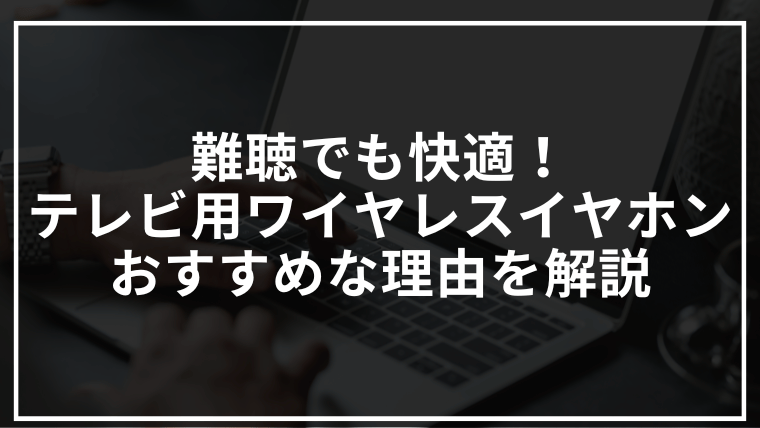障害者手帳なしでも大丈夫!軽度難聴者が使える就職支援サービスまとめ
「難聴だけど障害者手帳は持ってない……」
「片耳難聴で障害者手帳はもらえないけど、転職サポートして欲しい……」

そんな悩みやモヤモヤを抱えて転職活動に一歩踏み出せずにいる方、
意外と多いんです。

実はボク自身も、
片耳難聴を抱えながら何度も転職を経験してきました。
「片耳・軽度難聴」という“グレーな立場”で感じる不安、
とてもよく分かります
軽度難聴の方が実際に使える転職エージェントや支援サービスの選び方、
伝え方のコツが分かります。
「軽度難聴」の就職活動のリアル
① 片耳難聴は障害者手帳の対象??
まず気になるのは片耳難聴は公的に「障害」とされるのか
制度上の位置づけが気になるところです。
結論は、「基本的には、身体障害者手帳の対象にはなりにくい」です。
ただし、現実の職場や日常生活では支障が出る場面も多く見られます。
たとえば会議中に誰が話しているのか分かりにくかったり……
「障害」として認められていないけど、「健常」とも言いきれない。

そんな中間地点にいることで、支援も受けづらくなってしまうのが、
片耳・軽度難聴の大きなハードルなんです。
② 転職活動で感じる「支援の壁」と不安

「制度に該当しないなら、自分でなんとかするしかない」
と感じてしまう場面は多いかもしれません。
片耳・軽度難聴の方も、状況を丁寧に伝えれば、
対応してくれる支援サービスや企業もあります。

制度のグレーゾーンにいるからといって、
支援の対象外であると決めつける必要はありません。
③ 伝えづらい・伝え方がわからないという悩み
「難聴があるって、いつ・どうやって伝えればいいの?」
この悩み、本当に多いです。

ボクも最初の転職では、伝えるタイミングにすごく悩みました。
「話すことでマイナス評価されないか?」「そもそも理解してもらえるのか?」と不安になって、
何も言えずに失敗してしまった経験もあります。
でも今なら言えます。
「正直に、でも前向きに伝える」ことが大切なんです。
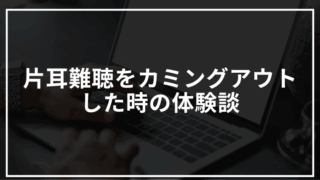
④ なぜ軽度の難聴だとサポートが受けづらいのか?
そもそも、なぜ片耳や軽度の難聴だとサポートが受けづらいのでしょうか?
障害者手帳という「制度の基準」があるから。
手帳があれば「障害者」として正式に認められているので、サポート対象にしやすい。
一方で、手帳がなければ「どの程度支援が必要なのか」が分かりづらく、
企業側の対応が難しくなるんです。
「特別な支援が必要なのか?」「配慮が必要なら、具体的にどうすればいいのか?」
といった受け入れ側の理解も、まだまだ進んでいないのが現状です。
⑤ 軽度・手帳なしでも相談できる場所はある??
「手帳がないと、誰にも相談できない」なんてことはありません!
一般の転職エージェント(リクルートやマイナビなど)でも、
登録時に「片耳難聴である」と伝えれば、可能な範囲で配慮してもらえるケースがあります。
また、「地方自治体の就労支援センター(自治体・地域型)、就労移行支援」では、
手帳がなくても相談に乗ってくれることが多いです。
ポイントは、「難聴があるから無理」と思い込まないこと。
たとえ軽度であっても、声をあげていいんです!

ボクは片耳難聴ですが事情を丁寧に説明し、
「マイナビエージェント」を利用して転職をした経験があります。
片耳・軽度難聴者が“実際に使える”転職サポート

手帳がなくても、片耳や軽度でも、相談できる場所はちゃんとあります。
制度の隙間に落ちてしまうような立場の人にとってこそ、
寄り添ってくれるサポートが必要なんです。
① 一般の大手転職エージェント(リクルート・マイナビなど)
「軽度・片耳難聴」でも利用できる転職エージェントの代表格が、
リクルートやマイナビなどの総合型エージェントです。
ボクも実際にリクルートエージェントを利用した際、
「聞き取りに不安がある」と伝えたところ、面談はチャット+メールで進行してくれました。
大手であればあるほど、多様な利用者層への理解が進んでいる印象があります。
ただし、自分から伝えないと気づいてもらえないので、
勇気を出して一言添えるのが大事ですよ。

ボク自身、マイナビエージェントを利用しましたが、
片耳難聴のことも含めて、丁寧な対応していただきました。
② 地方自治体の就労支援センター(自治体・地域型)、就労移行支援
意外と知られていないのが、
各自治体にある「ハローワーク」や、
発達障害者への支援を総合的に行うことを目的とした専門的機関「発達障害者支援センター」です。
ここでは、就職に関する悩みを相談できます。
相談員の方も福祉や就労支援の経験が豊富で、
「難聴だから」と断られることはほとんどありません。
ホームページでは情報が少ない場合があるので、
直接電話や訪問で問い合わせるのがベストです。

「難聴で困っているのですが、相談できますか?」と一度聞いてみる価値ありです。
障害者手帳が無くても使える支援機関まとめ表
| 支援機関 | 手帳なし (片耳・軽度など) | 主な支援内容 |
|---|---|---|
| ハローワーク(専門援助部門) | △ 相談によって対応(確認) | 職業相談、求人紹介、職場実習の手配 |
| 地域障害者職業センター | △ 要相談(医師の意見書等) | 就労評価、職場定着支援、アセスメント |
| 就労移行支援事業所 | △ 要相談(医師の診断書があれば可能) | 職業訓練、生活支援、就活サポート |
| 発達障害者支援センター(聴覚の相談にも対応) | ◎ 利用可 | 相談支援、環境調整アドバイス、連携支援 |
| 福祉機器の助成制度 | △ 自治体により異なる | 生活補助機器の支給・助成 |
◎=原則利用可能/△=条件により利用可(事前相談がおすすめ)
③ 選び方のポイント
「どれを選ぶべき?」と迷ったら、
まずは一番気軽にアクセスできる窓口から動いてみましょう。
すぐに相談したいなら「大手転職エージェント」。
地元志向や不安が強い方なら就労支援機関機関(自治体・地域型)
がおススメです。
相談=登録ではありません。

「話すだけ」でも、
一歩踏み出すきっかけになります。
軽度難聴者の転職活動(エージェント)の実際|登録から内定までの流れ

「転職エージェントって、どんな流れで進むの?」「何をいつ伝えたらいいの?」
そんな疑問や不安を持っている方も多いですよね。

ボクが実際に片耳難聴でエージェントを利用して転職した経験をもとに、
登録から内定までのリアルな流れと、気をつけてほしいポイントをまとめました。
「伝えるタイミング」や「求人選びの視点」など、ちょっとした工夫で転職活動はもっとラクになりますよ!
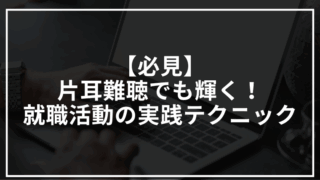
① 登録時に伝えたこと・伝えなかったこと
登録フォームで「片耳難聴」と書くか、少し悩みましたが……
結果として、最初の段階でしっかりと自分の状況を伝えましました。
エージェントさんも、「そうなんですね。分かりました。」と理解してもらいました。
この経験から感じたのは、「伝えること=マイナスになる」ではないということ。

事前に伝えておくことで、
安心して面談に臨める環境を整えてもらえるんですよね。
エージェントさんから企業側にあらかじめ難聴のことを共有してもらえたことも良かったです。
② 企業面談・面接での工夫と配慮のお願い
企業面談や面接では、
聞き取りに関する不安はなるべく早めに伝えるようにしました。
「すみません、聞き取りにくいことがあるかもしれません。その場合は、聞き返させていただきます」と、
丁寧に一言添えるだけでOK。

「配慮してください」じゃなくて、
「少しだけ工夫させて頂きます。」という伝え方が、とても効果的でした。
③ 求人選びで見ておきたい「音環境」とは
軽度・片耳難聴の方にとって、意外と重要なのが「音環境」の確認です。
たとえば、
- オープンスペースか?個室か?
- 電話業務が多いかどうか
- 周囲の音が反響しやすい作りか?
など、実際に働くうえでの“聞こえやすさ”って、
働きやすさに直結します。
求人票だけではわからない部分なので、
面談時に「職場の音環境が気になるため、事前に確認したい」と伝えると安心です。
④ 自分に合った職場の見つけ方
一番大事なのは、
「聞こえの悩みを無理に隠さないこと」です。
面接時に伝えることで落とされる会社もあるかもしれません。
でも、それは「自分に合わない職場」だっただけ。
理解がある企業は、最初から寄り添ってくれます。
配慮のある企業は、入社後も継続してサポートしてくれることが多いです。
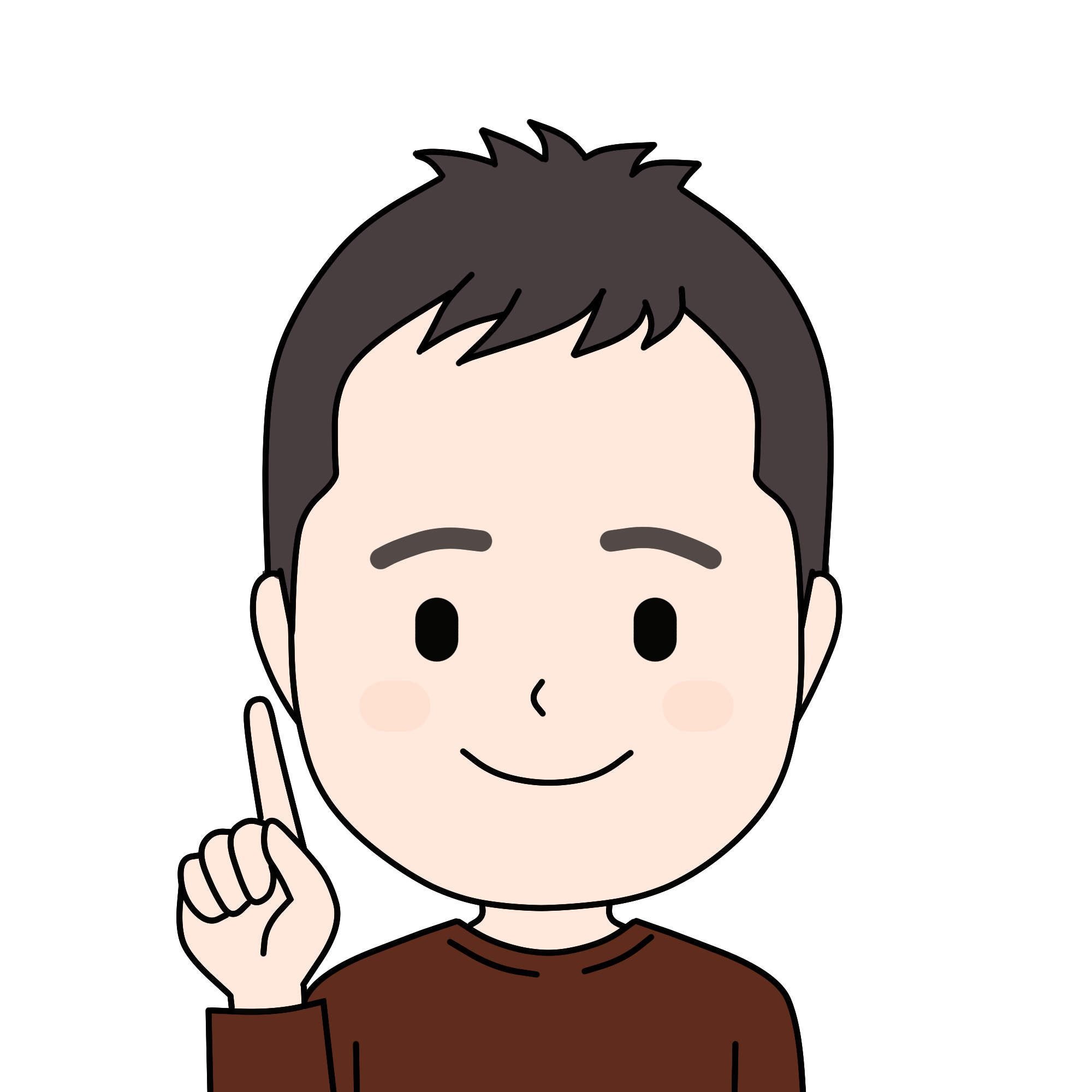
だからこそ、「自分の状況を率直に伝える勇気」を持つことが、
転職成功の第一歩なんです。
軽度でも諦めない。不安を伝えてもいい理由
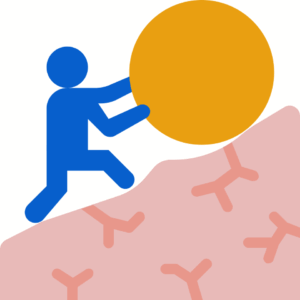
「軽度だから支援を求めちゃいけないのかな…」
そんなふうに思って、言葉を飲み込んでしまったこと、ありませんか?
でも、それって本当に悲しいことなんです。
どんなに軽く見られても、困っている気持ちは本物。
ここでは、「軽度」「片耳」「手帳なし」でも、
堂々と不安を伝えていい理由についてお話ししていきます。
① 「手帳がない」からといって支援を受けちゃダメなんてことはない
まず知っておいてほしいのは、
「手帳がない=支援を受ける資格がない」ということではないということ。
支援の多くは制度上、手帳を基準にしていますが、それはあくまで「入口の条件」。
本当に大切なのは、今「困っている」という事実なんです。
たとえば、「面接時の聞き取りが不安」「音環境がつらい」など、
小さな困りごとも立派な支援対象。
声をあげることで、ちゃんと対応してくれる人は必ずいます。
② 軽度でも伝えるだけで職場は変わる
ボクが実際に経験した話です。
転職先の初日で「片耳が聞こえにくいので、反対側から話しかけられると気づけないことがあります」と伝えたところ……
翌日、職場のデスク配置が“聞こえやすい側”に変ていただくことができたのです。
何気ない配慮かもしれません。
でも、それがあるだけで職場に安心感が生まれて、仕事にも自信が持てました。
こういった例は他にもたくさんあります。
伝えるだけで、あなたの働きやすさは大きく変わります。
③ やさしいエージェントに出会うコツ
どんなに実績があるエージェントでも、相性が合わないと話しづらいことってありますよね。
そんなときは、1社にこだわらず、
複数のエージェントに登録して比較するのがベストです。
たとえば、
- チャット対応してくれる
- 聞き取りの不安に寄り添ってくれる
- 必要以上に急かしてこない
こんな対応をしてくれるエージェントは、本当に信頼できます。

「この人なら安心して話せる」って思える存在に出会えるまで、妥協しなくて大丈夫。
ボクも2~3人担当者を変更してもらいました。笑
④ 少しの勇気が、転職の未来を変える

「話していいんだ」「相談していいんだ」と思えるだけで、
心はふっと軽くなります。

不安を伝えることは、決して弱さじゃありません。
むしろ、自分のことをちゃんと知ってもらう“勇気ある行動”です。
転職活動は孤独に感じることもあります。
でも、伝えた先に寄り添ってくれる人がいる。
あなたの声は、ちゃんと届きます。
よくある質問(FAQ)

ここでは、実際に多く寄せられる質問と、それに対するリアルで安心できる答えをまとめました。
① 片耳難聴だけでも相談していいの?
はい、もちろん相談してOKです。
たとえ「障害者向けの支援対象外」と言われることがあったとしても、一般の転職エージェントや支援窓口では、聞き取りに不安があることを伝えるだけで配慮してもらえるケースがあります。
“軽度だから” “片耳だけだから”と気にしなくて大丈夫です。
不安があるなら、それは相談すべき立派な理由なんです。
② 電話が苦手だけど対応してもらえる?
はい、最近では電話以外の手段も用意されているところが増えています。
たとえば、
- チャット形式での面談予約
- メールでのやり取り
- Zoomなどのビデオ通話+字幕表示

など、エージェントによってはかなり柔軟に対応してくれます。
「電話が苦手です」とひとこと伝えるだけで、やり方を調整してくれるケースも多いので、
まずは安心して問い合わせてみてくださいね。
③ 手帳がなくてもハローワークは使える?
はい、ハローワークは誰でも利用可能です。
障害者手帳を持っていない場合でも、一般窓口や相談ブースで転職相談や求人紹介を受けられます。
もし聴覚に関する悩みがある場合は、「専門援助部門(障害者支援担当)」を案内してもらえることもあります。
とくに地域によっては、手帳なしでも配慮してくれる場合も多いので、
遠慮せずにまずは相談してみましょう。
④ エージェントには何をどう伝えたらいい?
ポイントは「不安があること」と「配慮してほしい内容」をセットで伝えることです。
たとえば、
- 「片耳が聞こえづらく、会話中に聞き返すことがあります」
- 「オンライン面談は、チャット併用だと助かります」
- 「面接の際、聞き取りに配慮いただける企業が希望です」
といったように、前向きな姿勢を見せつつ、
具体的な要望を伝えると相手にも伝わりやすいです。
言いづらいことかもしれませんが、最初に伝えることで、その後がとってもラクになりますよ。

ボクの場合、エージェントが事前に片耳難聴のことを企業に伝えてくれたため、面接がスムーズに進みました!
まとめ|あなたに合う働き方、きっと見つかる。
誰かと比べる必要はありません。
あなたに合った働き方は、必ず見つかります。

相談できる場所や支援制度を上手に活用して、
「自分らしく働ける場所」への一歩を踏み出してみてくださいね。
参考資料
- 厚生労働省|障害者の雇用支援
- 独立行政法人 高齢・障害・求職者雇用支援機構(JEED)
- 全国発達障害者支援センター協議会
- dodaチャレンジ公式、ランスタッドチャレンジド、デフワークス、LITALICO仕事ナビ
- 各自治体の福祉課サイト(例:東京都福祉保健局など)